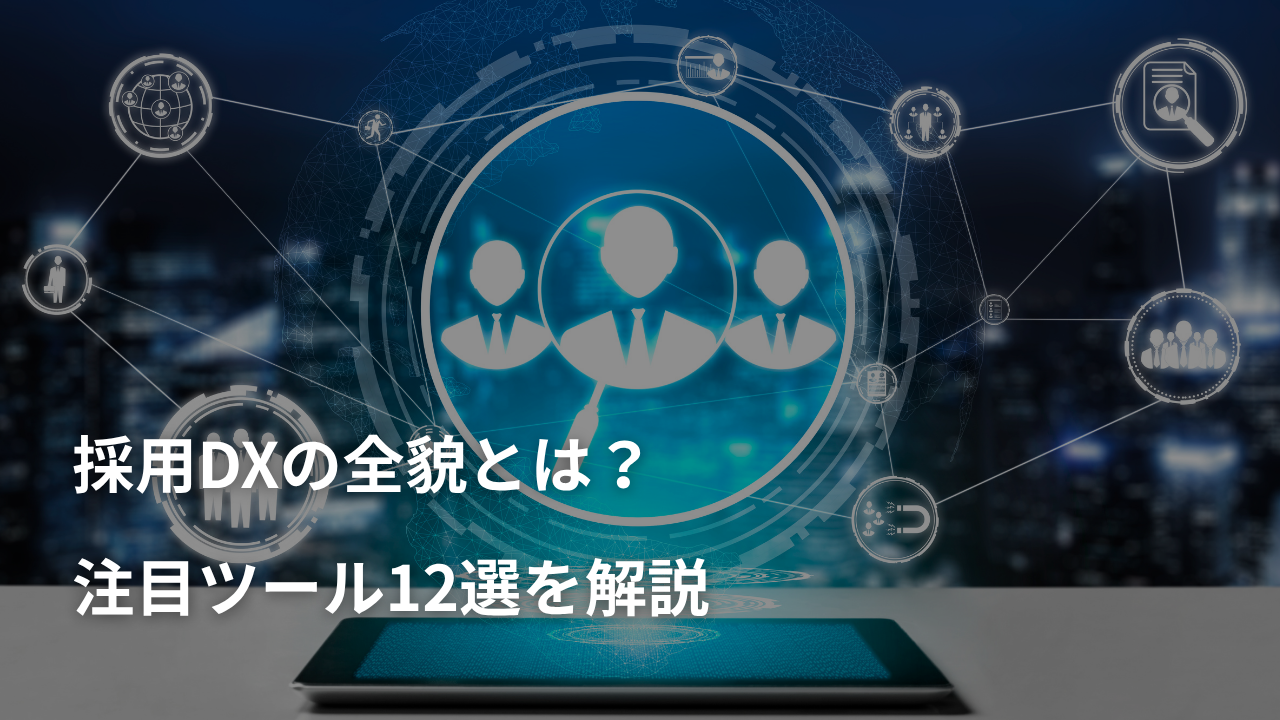
SHARE
採用DXの基礎知識と背景にある考え方
DXの意味と目的とは?企業が変革を迫られる理由
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、「ICT技術の浸透によって人々の暮らしや社会がより良い方向へ変化すること」を指します。平成30年に経済産業省が策定した「DX推進ガイドライン」では、企業の変革として以下のように定義されています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
つまり、DXとは単なるIT導入ではなく、企業の根幹にある価値提供や業務のあり方そのものをデジタルで革新する取り組みです。
採用DXの定義と果たす役割とは
この概念を人材採用に当てはめたものが「採用DX」です。企業がデジタル技術を活用して既存の採用業務やプロセスを再構築し、採用活動を効率化しながら、より自社に合った人材を獲得・定着させることが目的です。
採用DXは、単なる採用業務の効率化にとどまらず、企業が抱える人手不足やミスマッチといった根深い課題を解決するカギとなります。
なぜ今、採用DXが求められるのか?背景と時代の流れを解説
人手不足が続く今、採用市場での競争が加速している
近年は「売り手市場」が続き、優秀な人材の獲得競争が激化しています。厚生労働省の調査では、2023年の求人充足率は過去半世紀でも最低水準となり、人口減少を背景に人手不足が長期化すると予測されています。
このような状況では、限られた人材資源をいかに効率的かつ戦略的に確保するかが問われており、採用担当者が“戦略実行型”にシフトするための支援ツールとしてDXの導入が注目を集めています。AIによるマッチング支援やSNSとの連携機能など、採用活動の精度と効率を同時に高める技術も進化しています。
コロナ禍を契機に変わる働き方と採用の在り方
新型コロナウイルスの影響も、採用活動のDX化を大きく後押ししました。経団連の調査によると、約9割の企業が新卒採用の面接や広報活動をWeb上で実施しており、多くの企業がオンライン採用の有用性を実感しました。
また、コロナ禍を通じて求職者の働き方に対する価値観も変化し、テレワークや時短勤務、フリーランスといった柔軟な働き方が一般化しています。こうした変化に対応するには、従来の広告掲載型採用だけでは不十分です。今後は、AIによるスクリーニングや候補者理解を深めるデータ分析、ブランディングを支えるSNS運用など、戦略的なDXがますます重要になっていくでしょう。
採用DXで得られる5つの効果とは?
1. 採用業務を自動化し、作業負担を軽減する
採用活動には、求人作成・応募管理・日程調整・連絡業務など、多くのバックオフィス作業が伴います。これらの業務はDX化によって自動化が可能であり、担当者はより付加価値の高い業務に専念できるようになります。
特に以下の業務は、自動化によって大幅な効率化が期待できます。
- 求人広告の作成と出稿
- 応募者情報の取り込み・転記
- 応募者情報の管理
- 選考の日程調整・連絡
- 選考結果の通知やフォロー連絡
- 採用に関するデータの集計
記載漏れや送信ミスといったヒューマンエラーのリスクも軽減され、業務の正確性とスピードが格段に向上します。
2. 採用活動のデータを一元管理し、分析で改善に活かす
求人媒体ごとの応募者数、選考通過率、面接評価など、採用に関するあらゆるデータを1か所に集約・可視化できるのもDXの利点です。
これまでは散在していた情報を蓄積・分析し、グラフ化やレポート化することで課題や改善ポイントを明確にできます。こうしたデータは、次回以降の採用戦略にも活かされ、より精度の高いPDCAが可能になります。
3. 適材適所を実現するマッチング力の強化
AIや適性検査ツールを活用すれば、求職者の特性と自社文化との相性を客観的に測定できます。これは、面接官の主観による評価に頼りすぎることで生じるミスマッチを回避する手段にもなります。
例えば、活躍している社員の行動特性をAIに学習させ、応募者との適合度を測る仕組みを構築することで、採用の精度と成功率を同時に向上させることが可能です。
このようなDX化によって選好のミスマッチによる内定辞退や早期離職も減らせるでしょう。
4. 採用の成果を引き上げ、認知拡大へつなげる
採用DXにより、個別の採用課題を一つひとつ解決することで、結果として「採れる力」が強化されます。空いた時間や可視化された情報を活用して、候補者との接点づくりや関係構築といったブランディング施策にリソースを配分することも可能です。
SNSなどのメディアとの親和性が高いツールも増えており、母集団形成から応募促進までを戦略的に設計できるようになります。
5. 無駄な出費を抑え、コストパフォーマンスを向上
採用ツールには導入費用や運用コストがかかりますが、業務効率化やミスマッチ防止による採用単価の低下を通じて、全体のコストを抑えることが可能です。
また、ツールを選定する際には「自社の課題解決にどの機能が必要か」を明確にしておくことで、不要なオーバースペックを回避できます。各社が提供する多機能型・特化型ツールの特徴を比較しながら、自社に最も合った製品を導入することが成功のポイントとなります。
採用DX導入の流れをステップごとに解説
採用DXを成功させるには、単にツールを導入するのではなく、導入の目的や課題を明確にしながら段階的に進めることが大切です。明確な目標設定があれば、自社に必要な機能も選定しやすくなります。
採用DXを進める基本ステップは以下の4つです。
- 自社の採用上の課題を可視化・整理する
- 採用の目的と採用すべき人材像を明確にする
- 自社に合った採用ツールを見極めて導入する
- ツールの活用状況を見直し、改善へとつなげる
それぞれの手順について、具体的に解説します。
1. 自社の採用上の課題を可視化・整理する
最初に行うべきは、自社が抱えている採用課題を明確にすることです。
たとえば「求める人材が採用できない」という問題がある場合、その背景としては以下のような原因が考えられます。
- そもそも応募数が少ない
- 応募者は多いが求める人材がいない
- 選考途中で離脱する人が多い
原因によって必要な対策や導入すべきツールも変わってきます。採用のどの段階に課題が潜んでいるのかを分析し、根本原因を見極めましょう。
2. 採用の目的と採用すべき人材像を明確にする
次に、採用DXを導入する目的をはっきりとさせましょう。解決したい課題に対して、どのような状態を目指すのかを明確にし、KPI(重要業績評価指標)も設定しておくと効果検証がしやすくなります。
たとえば「ミスマッチの削減」を目的とするなら、どのような人物像が自社に合っているかを明確にし、面接や評価基準の基盤として活用することが重要です。目的や具体的な人物像が曖昧なままでは、導入したツールも十分に機能しません。あらかじめしっかり決めておきましょう。
3. 自社に合った採用ツールを見極めて導入する
目的とターゲットが明確になったら、それに合う採用ツールを選定します。
採用ツールには、大きく分けて以下の2タイプがあります。
- 一括型:採用活動全体を管理できるオールインワン型
- 特化型:面接日程調整や適性検査など個別課題に特化
使いこなせない機能があってもコストは発生するため、前段で分析した課題や目的に照らして、必要な機能をしっかり絞り込みましょう。
導入後は、採用活動全体の流れを最適化するため、ツールと既存プロセスとの連携も意識しながら再設計を行うことが重要です。
4. ツールの活用状況を見直し、改善へとつなげる
導入した採用DXの効果は、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回しながら検証・運用していくことが欠かせません。
例えば、事務工数の削減効果などは早期に実感しやすいですが、ミスマッチの改善やブランディング強化などは成果が可視化されるまで時間が必要です。
目標達成に向けて必要なデータを定期的に蓄積・分析し、改善点を明らかにしながら採用プロセスの精度を高めていきましょう。
今注目されている採用DXツール12選を徹底紹介
採用DXを導入する際は、「自社が何を解決したいのか」によって必要なツールが変わります。ターゲット層や目的を明確にしたうえで、機能・価格・運用性などを見極めることが重要です。
近年では多様な採用課題に対応できるよう、採用DXツールの選択肢も豊富になっています。この章では、ツールを以下の2カテゴリに分けて紹介します。
- 採用業務を一括管理できる総合型ツール5選
- 特定の採用課題を解決するツール7選
採用業務を一括管理できる総合型ツール5選
一括型の採用DXツールは、応募獲得から内定者フォローまで幅広い業務を自動化、効率化できるのが特長です。複数の工程を一元管理したい企業におすすめです。
今回は以下の5つのツールをご紹介します。
- ジョブカン採用管理(株式会社Donuts)
使いやすさとコストパフォーマンスに優れた中小企業向け定番ツール。 - HRMOS採用(株式会社ビズリーチ)
データ分析とサポートが充実した、大手企業にも対応可能なツール。 - 採用係長(株式会社ネットオン)
自社採用サイトを簡単に作成でき、求人検索エンジンと自動連携可能。 - タレントパレット(株式会社プラスアルファ・コンサルティング)
適性検査や人材データの一元管理で、マッチ度の高い採用を実現。 - ミイダス(ミイダス株式会社)
活躍人材の特性分析で、マッチング精度を高められる診断機能が強み。
ご希望であれば、同様に「特定の採用課題を解決する専門ツール7選」も箇条書き
ジョブカン採用管理|株式会社Donuts
ジョブカン採用管理は、「ジョブカン」シリーズの一つで、累計25万社以上の導入実績を誇る一括型採用ツールです。
特長:
- 採用サイトの作成から応募者管理、進捗管理、データ分析まで対応
- 初めての担当者でもわかりやすいシンプルでわかりやすい操作性
- LINE連携でコミュニケーション効率を向上
- 求人ごとの状況をリアルタイムで把握できるダッシュボード搭載
- 10種類以上の求人媒体と連携し、応募者情報の自動取り込みが可能
料金:
- 無料プラン
- LITEプラン(月額8,500円〜)
- STANDARDプラン(月額30,000円〜)
採用係長|株式会社ネットオン
簡単に採用サイトを作成できる手軽さが強みの採用DXツール。文章作成の自動化機能などにより、経験が浅い担当者でも安心して運用できます。
特長:
- 自社採用サイト作成→求人検索エンジン5社へ一括連携→迅速に採用活動をスタート
- 応募者情報ややり取りも一括管理可能
料金:
- 無料トライアルあり
- スモール(月額9,800円)
- ライト(月額19,800円)
- ベーシック(月額25,800円)
- プロ(月額39,800円)
- エンタープライズ(月額59,800円)
タレントパレット|株式会社プラスアルファ・コンサルティング
人材データを軸にしたあらゆる採用活動を一元管理できるオールインワン型のツール。適性検査や性格傾向の分析で人材のミスマッチのリスクを削減可能です。
特長:
- 採用から育成・配置までを統合的に管理可能
- 人材情報の一元化により業務を効率化
- 大手企業での導入実績も多数
料金: 要問い合わせ
ミイダス|ミイダス株式会社
マッチング機能に特化したツール。採用後の活躍可能性まで見据えた診断機能があり、客観的な人材分析に基づいて、自社にあった候補者を採用していく力を特に強化したい企業におすすめです。
特長:
- 求人掲載や応募者管理の自動化や効率化を簡単な操作で行える
- 「フィッティング人材分析」で社内の人材の分析を元に自社に合う人材を可視化
- 各種診断結果は配属や育成にも活用可能
料金:
- 無料トライアルあり
- 正式プランは要問い合わせ
特定の採用課題を解決する専門ツール7選
次に、求人媒体との連携や面接など、個別の課題解決に重点を置く採用DXツールをご紹介します。
今回は以下の7つのツールをご紹介します。
- harutaka(株式会社ZENKIGEN)
オンライン面接や動画選考で、選考プロセスの質とスピードを向上。 - engage(エン・ジャパン株式会社)
求人作成・管理が無料で行え、手軽に始められる初級者向けツール。 - MyRefer(株式会社TalentX)
リファラル採用を支援する専門ツール。制度設計や社内広報まで対応。 - エアリク(株式会社リソースクリエイション)
採用に特化したSNS運用代行サービス。ブランディング強化にも貢献。 - ミキワメ(株式会社リーディングマーク)
活躍人材の特性診断や従業員サーベイで、ミスマッチや離職を防止。 - PRaiO(株式会社マイナビ × 株式会社三菱総合研究所)
AIによる書類選考支援で、選考工数を大幅削減できる効率化ツール。 - miryo+(株式会社Legaseed)
志望度の可視化・アラート機能など、内定辞退や早期離職対策に有効。
harutaka(株式会社ZENKIGEN)
オンライン面接に特化し、選考のスピードと質を向上させるツール。
特長:
- エントリー動画で事前に人柄・熱意を確認可能→選考期間の短縮
- ライブ・録画面接にコメント機能で定量評価
- AIによるリアルタイム面接フィードバック機能→面接の質の担保
- ITに不慣れな人でも操作しやすく、導入前のサポートも充実
料金:
- 年間登録者数に応じたプラン
- 14日間の無料トライアル
- engage(エン・ジャパン株式会社)
求人掲載から応募管理などの基本機能を無料で使えるため初めての採用ツールに最適。
特長:
- 求人媒体との連携やスマホ対応ページ作成が簡単
- IndeedやGoogleしごと検索と連携
- フォローツール・適性検査も一部無料で利用可能
料金:
- 基本機能は無料(一部有料オプションあり)
- MyRefer(株式会社TalentX)
リファラル採用に特化し、高いマッチング率を誇る採用DXツールです。
特長:
- リファラル制度設計~定着化までトータル支援
- 専任担当者によるコンサルティングサポート
- (サポート内容)
- 独自のリファラル採用制度を設計
- 社内広報・プロモーション施策を支援
- 採用活動の分析・レポート作成をサポート
- 入社後の定着促進とファン化を支援
- ATSと連携可能で運用効率も高い
料金:
- 要問い合わせ
- エアリク(株式会社リソースクリエイション)
SNS採用運用をまるごと委託可能なSNS特化型支援サービスです。
特長:
- 専属チームが投稿内容から画像の生成、分析まで対応
- SNSを活用したブランディングと母集団形成が可能
- 中小企業での実績も豊富(例:社員20名→2,300名応募)
料金:
- 初期費用:300万円
- 月額:10万円~(※税抜・更新回数により変動)
- ミキワメ(株式会社リーディングマーク)
マッチングと定着支援に強みを持つ適性検査・サーベイツールです。
特長:
- 性格診断結果に基づき、採用・配属基準を策定
- 活躍可能性をS~Eの14段階で評価
- 面接用質問の自動生成、幸福度調査機能あり
料金:
- 適性検査:1人550円(税込)
- 月額システム利用料:44,000円~(税込)
- PRaiO(株式会社マイナビ×株式会社三菱総合研究所)
AIによるエントリーシート評価が特長で採用計画立案・選考・振り返りまでの効率化を図るDXツールです。特に書類選考の効率化にお勧めのツールとなっています。
特長:
- 書類選考の優先度をAIがスコアリング
- 応募情報の学習を通じて選考の工数を削減し、選考効率を大幅改善
- 専門知識不要で直感的に操作可能
料金:
- 無料トライアル診断あり
- 要問い合わせ
- miryo+(株式会社Legaseed)
志望度の可視化やアラート機能で候補者フォローに強いツール。
特長:
- 志望度の変化を検知してアプローチ可能
- アクションすべきタイミングをアラートで通知
- 自動化機能と魅力づけ支援機能を併せ持つ
料金
- 要問い合わせ
採用DXの導入事例|中小企業における実践と成果
この章では、採用DXツールの導入によって、業務効率や採用成果に具体的な変化があった中小企業の事例をご紹介します。
各社ともに、採用管理システム(ATS)やAI評価ツール、動画面接システム、外部連携機能などのDXツールを活用し、「手間のかかる採用業務の削減」と「採用の質の向上」の両立に成功しています。
事例1. 小売業A社|動画面接×AI評価で選考スピードが大幅改善
背景と課題:
- 年間100名以上を採用する中で、一次選考で実施していた動画面接のジャッジに担当者の時間が奪われていた
- 応募者数が多く、感覚的な判断ではマッチ度を評価しづらい
導入ツールと施策:
- 動画面接ツールにAI評価機能を追加(※例:harutakaなど)
- 応募者の動画をAIが解析し、評価スコアの高い順に並び替え
- 担当者は高評価者のみを確認し、判断時間を大幅に短縮
導入後の成果:
- ジャッジ対象数を約50%削減
- 面接スケジュール調整も自動化でき、1人あたりの選考リードタイムが短縮
- 「人柄重視」の判断が属人性なく可能に
事例2. サービス業B社|ES評価のAI化で選考工数を70%削減
背景と課題:
- エントリーシート(ES)を1,000件以上手作業で確認しており、判断にバラつきもあった
- 採用担当が限られた時間で的確に書類を見極める必要があった
導入ツールと施策:
- AIによるES解析ツール(※例:PRaiOなど)を導入
- 評価指標(コミュニケーション力、主体性など)をスコア化し、ランキング形式で抽出
- 高スコア群に絞って一次面接を実施
導入後の成果:
- 書類選考の工数を70%削減
- 応募者対応に割ける時間が増え、フォローアップも強化
- 「評価の見える化」により、納得感のある判断が可能に
事例3. 住宅不動産業C社|交通費精算業務をDX化し、ミスとやり取りをゼロに
背景と課題:
- 面接時に発生する交通費精算処理(申請内容の確認・経理連携など)が煩雑
- 対応ミスや確認の手戻りも多く、応募者からの信頼に関わるリスクもあった
導入ツールと施策:
- 採用管理システム(ATS)と外部決済システムを連携
- 交通費申請をWebフォームに統一し、ATS上で申請・承認・支払い処理を完結
- 申請基準をテンプレート化し、属人的な判断を撤廃
導入後の成果:
- 処理業務の時間を約80%削減
- 申請から振込までのリードタイムが明確になり、トラブルもゼロに
- 面接後のフォロー精度が上がり、内定辞退率も改善
まとめ:自社に最適な採用ツールを選び、採用DXで競争力を高めよう
デジタルツールは日々進化しており、採用活動への活用も今後さらに一般化していくと考えられます。この記事では、採用DXの推進に役立つトレンドツール12選をご紹介しました。
ただし、ツールはあくまで手段です。導入に際しては「自社が何を実現したいか」を明確にしたうえで選定することが、成果につながる第一歩です。
採用DXを成功させるためのステップは、次の通りです。
- 自社が抱える採用課題の現状分析
- 採用活動の目的や求める人材像の明確化
- 目的に合う採用DXツールの選定・導入
- 導入後の運用と効果の検証
採用DXツールは多くが直感的に使える仕様になっていますが、事例にもあったように、より高い効果を目指す場合は、専門知識と実績を持つ外部パートナーのサポートを得ることも有効です。自社の状況に合わせて導入しましょう。



